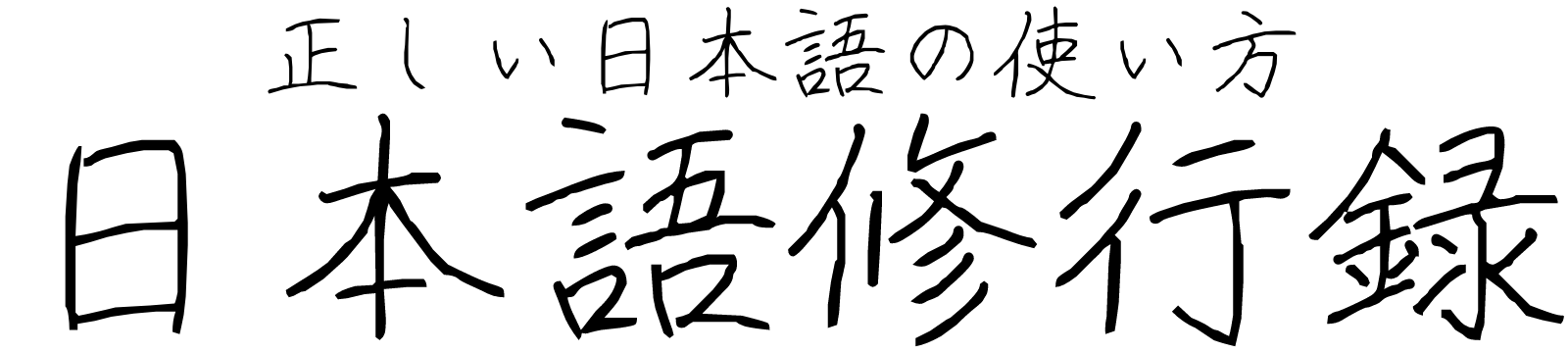この記事は、動詞の用法の解説記事です。
今回解説する動詞は、「頂く/戴く/いただく」です。
この記事で解決できるお悩み
- 頂く/戴く/いただく のそれぞれの意味を知りたい!
- 頂く/戴く/いただく の使い分けについて知りたい!
- いただく をひらがな表記するべき場合を知りたい!
- 敬語としての「いただく」の使い方を知りたい!

「頂く/戴く」の意味とその違いは?
「頂く/戴く」の使い方は?
「頂く/戴く」は、「食べる」「飲む」「もらう」の謙譲語として使います。
- 謙譲語とは?
-
謙譲語とは、自分の所作をへりくだる表現のことです。
自分の所作をへりくだることにより、相対的に相手を高め、敬意を表すことができます。
「頂く/戴く」の例文
- お手紙を頂くのを楽しみにしています。
- お中元を頂いた。
- 冷めないうちに、頂きます。
「頂く/戴く」の違いは?
頂く/戴くは同じ意味であるため、どちらを使っても文法上は問題ありません!
新明解国語辞典などでは、「頂く/戴く」は一語として掲載されており、区別されていません。
ただし、「戴く」は常用漢字ではありませんので、新聞などの公用文では「戴く」は全て「頂く」で統一されています。
どちらを使用しても文法上は問題ありませんが、「頂く」に統一するのが無難であると思います。
「戴く」は常用漢字ではないため、「頂く」を使用することをお勧めします。
「頂く/いただく」の違い・使い分けについて
補助動詞としての「いただく」の意味
「いただく」は、補助動詞としても機能します。
補助動詞について
皆さんは、「補助動詞(形式動詞ともいう)」をご存知でしょうか。
- ”補助動詞”とは
-
補助動詞とは、本来の言葉の意味が薄まり、ほかの語の後に続いて、その直前の文節の意味を補う役割を果たす動詞のことです。
- ”本来の言葉の意味が薄まる”とは
-
たとえば、「試してみる」という言葉。
この「みる」は、「視覚に入れる」という本来の言葉の意味は持っていませんよね。
「試してみる」や「教えてください」は、本来の動詞そのものの意味が薄まった”補助動詞”です。
「いただく」は、まさにこの補助動詞にあたります。
先日、当ブログにてご紹介した「言う(いう)」も、補助動詞として機能します。

「いただく」が補助動詞として使用されるのは、例えば、以下のようなときです。
以下の文章で使用される「いう」は、どれも本来の意味では使用されていませんよね。
「いただく」の意味と例文

①他者から行為を受け取る の意味で使用されたときの例文をご紹介します。
- 本日のパーティーはお楽しみいただけたでしょうか?
- 遠路はるばるお越しいただき、ありがとうございます。
- それでは、後日改めてお電話させていただきます。
②「させてもらう」の謙譲語 としての意味で使用されたときの例文は、こちらの記事よりご覧ください。
補助動詞として使用するときの表記について 頂くVSいただく
”令和3年 新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)”によると、補助的動詞を使用するときには、仮名で表記するように規定されています※。
※13頁 ア参照
ですが、これはあくまで公用文のルールです。
辞書には、全て「言う/云う」の意味として記載されていますし、「ひらがなで表記するべきである」といったような注意書きもありません。
つまり、補助動詞として使用したいときに漢字で表記しても誤りではありません。
ただ、個人的には公用文のルールに合わせるべきであると思います。
そもそも、なぜ公用文のルールが定められているのでしょうか?
”令和3年 新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)”には、以下のように記されています。
公用文は、読み手に過不足なく理解され、また、信頼され、それによって必要な行動を起こすきっかけとされるべきである。
令和3年 新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)より
要するに、公用文のルールとは、読み手に伝わりやすい文章を書くためのルールであるということです。
伝わりやすい文章を書くことは、公用文に関わる公務員や士業に携わる者に限られず、誰もが目指すべきことです。
したがって、表記についての厳密な規定はなくとも、公用文のルールに従うのが良いのではないか、というのが自論です。
以上の理由から、「いただく」を補助動詞として使用するときには、「いただく」と表記するべきであると考えます。
【誤用に注意】敬語としての「いただく」の正しい使い方
注意点①相手の動作には「いただく」を使用しない
前述したとおり、「頂く/戴く/いただく」は、全て謙譲語として使われます。
謙譲語とは、その動作の主体(=自分)を下げて表現することで、間接的に動作を受ける主体(=相手)を上げる表現です。
したがって、「頂く/戴く/いただく」は自分の行為にのみ使用します。相手の行為に使用すると、失礼にあたるので注意しましょう。
「食べる」「飲む」の意味で「頂く」を使用したときは、「召し上がる」と言い換えると良いです。
- お料理が冷めないうちに、どうぞ頂いてください。
- お料理が冷めないうちに、どうぞ召し上がってください。
注意点②二重敬語に注意する
二重敬語とは、一つの語に対して、同じ種類の敬語を2度使ったものを指します。一般的に、二重敬語は良くないとされています。
二重敬語の代表例としては、こちらの記事でご紹介した「拝見いたしました」等が挙げられます。
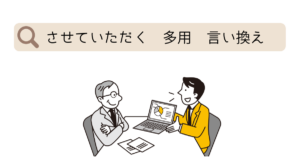
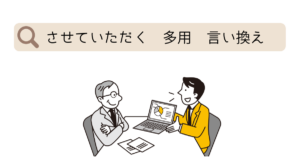
前述したとおり、「頂く/戴く/いただく」は、全て謙譲語として使われます。したがって、他の謙譲語と一緒に使用することはできません。
ただし、尊敬語と一緒に使用する分には問題ありません。
例えば、「ご覧いただく」という表現は、「見る」の尊敬語である「ご覧」と、「もらう」の謙譲語である「いただく」が組み合わさった表現であるため、二重敬語ではありません。
尊敬語+謙譲語であれば二重敬語ではありません。謙譲語+謙譲語(または尊敬語+尊敬語)の場合は、二重敬語です。
まとめ:頂く/戴く/いただくの違い・使い分け・敬語で使用するときの注意点
最後に、今までご説明したことをまとめます。
まとめ:頂く/戴く/いただくの違い・使い分け・敬語で使用するときの注意点
- 「頂く/戴く」は、「食べる」「飲む」「もらう」の謙譲語として使う。
- 「戴く」は、常用漢字ではないため、「頂く」で統一して表記される。
- 補助動詞として「頂く/戴く」を使う場合、「いただく」と表記するのが良い。ただし、「頂く/戴く」と表記しても間違いではない。
- 公用文のルールでは、補助動詞として使用する場合には「いただく」と表記することが推奨されている。
- 敬語として使用するときは、①相手の動作に対して「いただく」を使用しないこと②二重敬語にならないようにすること の2点に注意する。
如何でしたか。
この記事が、少しでも皆さまの理解の助けになれば幸いです。
- 文化審議会国語分科会(2021)「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」文化庁
- 小田順子(2021)「例話時代の公用文 書き方のルール」学陽書房
- 山田忠雄ほか(2009)「新明解国語辞典(第6版)」三省堂
- 菊池捷男”公用文の書き方 5 “動詞は漢字で,補助動詞は平仮名で書く”と覚えるべし”マイベストプロ、2014年9月6日 公開(最終閲覧日:2021/12/13)